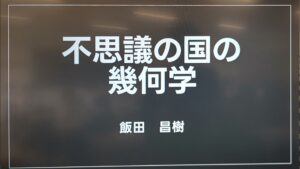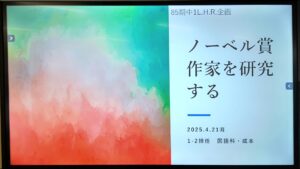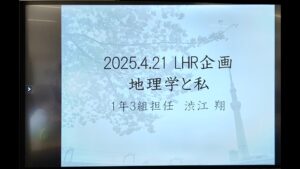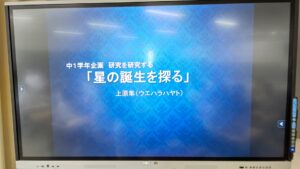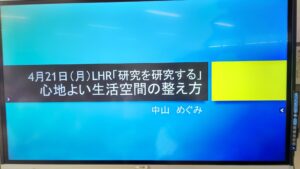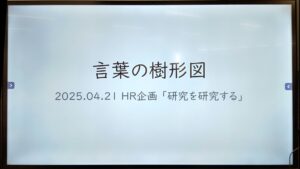『研究を「研究」する』-中学1年生とともに考える。
TOHO Today中学
4月に入学したばかりの85期中学1年生。入学から1ヶ月ほどが経過し、学校やクラスメイトにも慣れてきて、元気に日々を過ごしています。
85期生のスタートとなる今年度の学年目標は「風をあつめて」。これには、学びや行事や自分の目標などに向けて、さまざまな要素を主体的に集めながら、自ら学校生活をつくり出していって欲しい・・・そんな思いが込められています。
□
□
これを具現化する第一歩として、夏休みの自由研究を通して「学びの風」を集めて欲しい・・・。このような意図から、中1クラス担任自身がこれまで研究してきたこと・取り組み続けていることについて、6人のクラス担任が生徒たちにレクチャー(講義)する機会を設けました。題目は『研究を「研究」する』。日常の勉強の延長にある「学び」とは、「研究」とは何か、生徒たちと一緒に考えてみました。
□
□
以下6種の講義のなかから、生徒たちは自分の興味のあるものを1つ選び、もう1つは、新しい興味への出会いを期待して教員の方でランダムに振り分けました。
「不思議の国の幾何学」 「ノーベル賞作家を研究する」 「地理学と私」
「星の誕生を探る」 「心地良い生活空間の整え方」 「言葉の樹形図」
□
□
講義終了後『「研究をする」時に大切なことは何?』という問いかけを彼らにしました。以下に彼らの「答え」をご紹介します。
・少しわかっただけでやめるのではなく、疑問への解答からまた疑問を持つ・・・を繰り返していき、研究をとめないこと。
・そのことに熱中して、長い時間をかけても飽きたりせずに、計画的に継続させること。
・こだわること。自分を信じること。自分がやると言ったらあきらめないこと。チャンスを逃さないこと。
・他人のデータではなく、自分のデータを使うこと。
□
□
85期の生徒が入学した翌日に、私たち教員から生徒たちに向けて「学ぶとはどういうことだろう?」という「問(とい)」を投げかけました。そして、これまで生徒たちが頑張って取り組んできた勉強と、その少し先にある「学び」に、彼らが主体的に向かっていって欲しい・・・という思いをどうしたら伝えられるかを考えたときに、「私たち教員がおもしろいと思っている学びを、生徒たちに紹介してみよう」という思いに行き着きました。
□
□
「主体的に学ぶこと」は決して簡単ではありませんが、今回のHRの取り組みに対する生徒たちの反応は、私たちの予想をはるかに超える、輝く言葉であふれていました。桐朋という学び舎で生徒たちと共に学んでいきたい・・・と、あらためて大きな期待を持ちました。(中1担任 M.N)