2023年度 中央委員会議長、高校総務委員長 石原佑高
 2023年度中央委員会議長・高校総務委員長を務めさせていただいております、石原佑高です。この場を借りてご挨拶申し上げます。
2023年度中央委員会議長・高校総務委員長を務めさせていただいております、石原佑高です。この場を借りてご挨拶申し上げます。
この一年は本当に様々な出来事がありました。特に、新型コロナウイルス感染症の「5類引き下げ」によるコロナ禍の終結は「日常」を取り戻したという点で社会に大きな変化をもたらした出来事と言えるでしょう。しかし、我々がコロナ禍終結後に取り戻した「日常」はコロナ禍以前の「日常」とは全くの別物でした。ロシアによるウクライナ侵攻を初め、イスラエルでの紛争等の国際情勢の不安定化や生成AIをはじめとする新しい技術の発達…この一年は、我々が「日常」を取り戻した年であると同時に、こうした新しく、そして不安定な社会に「新たな秩序」を求め続けた年でもあったと思います。もちろん、それは桐朋という小さなコミュニティにおいても言えることであり、生徒会もこうした変化にどう適応していくかが問われた一年でした。
2学期から一部学年へ導入されたICT機器は、今後の学校生活を大きく変化させるものとして注目を集めました。そこで、我々は定期的に生徒の意見を集約し、提言書を提出した他、先生方との意見交換会を企画。環境・ルール作りに生徒自身が直接関わることで、生徒の主体的な学びの実現を目指しました。また、生徒からの根強い要望のあった、自販機等の校内設備へのIC決済の導入について、導入の有無、導入時の利点・欠点について、より多角的な視点から全生徒を巻き込んだ議論を実施し、請願書を提出しました。
これらの取り組みは一貫して、「変容する社会の中で自らの学校環境を自ら考え、議論し、創り出す。」ということを念頭に置いたものであり、桐朋の「自主」の精神のもとで、新たな学校環境への適応を試みたものでした。また、その過程で全生徒そして全教員を巻き込み、対立よりも協調によって課題解決を目指せたことは、桐朋と桐朋の生徒会の誇るべき点であると思います。
こうしてみると、桐朋における「新たな秩序」は間違いなく、「個人」ではなく「全員」で創成されていくものであると言えるでしょう。確かに、民主主義の危機が叫ばれる今日においては、圧倒的なカリスマ性を備えたような特定の「個人」の登場の方が期待されるのかもしれません。しかし。いやだからこそ、如何なる困難が訪れようとも、私はこの先も桐朋という環境が「全員」の力によって創られ続けていくものであると確信しています。
そして、その中で先代が紡ぎ続けてきた「自主」の精神と、現状から目を逸らさずに仲間との対話を続けようとする姿勢のもと、桐朋中学・高等学校生徒会が「生徒のための生徒会」として、その役割を果たし続けることを心より期待しています。

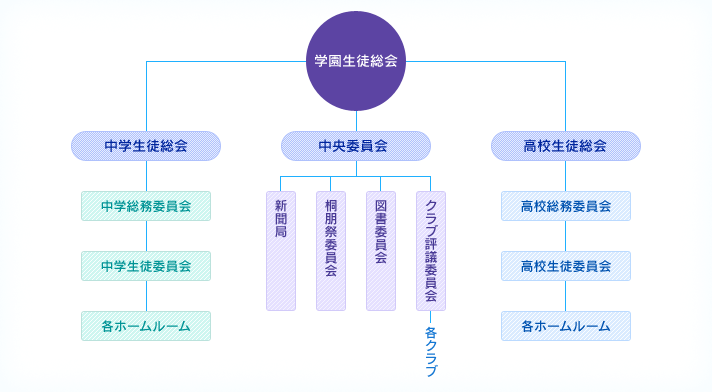


 2022年度、中央委員会議長・高校総務委員長を務めております土田淳真です。この場を借りてご挨拶申し上げます。
2022年度、中央委員会議長・高校総務委員長を務めております土田淳真です。この場を借りてご挨拶申し上げます。 2021年度の高校生徒会総務委員長の森河正平です。
2021年度の高校生徒会総務委員長の森河正平です。 2020年度中央委員会議長、高校総務委員長を務めさせていただいております、高校2年の章子昱です。今年度の生徒会活動もほとんど終了してしまいましたが、この場を借りてご挨拶させていただきます。
2020年度中央委員会議長、高校総務委員長を務めさせていただいております、高校2年の章子昱です。今年度の生徒会活動もほとんど終了してしまいましたが、この場を借りてご挨拶させていただきます。 2019年度中央委員会議長、高校総務委員長をさせていただいております、高校2年の菊地晃成です。今年度の生徒会活動もほとんど終了してしまいましたが、この場を借りてご挨拶をさせていただきます。
2019年度中央委員会議長、高校総務委員長をさせていただいております、高校2年の菊地晃成です。今年度の生徒会活動もほとんど終了してしまいましたが、この場を借りてご挨拶をさせていただきます。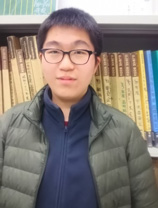 2018年度中央委員会議長をさせて頂いております、高校2年の服部勇気です。この場を借りてご挨拶させて頂きます。
2018年度中央委員会議長をさせて頂いております、高校2年の服部勇気です。この場を借りてご挨拶させて頂きます。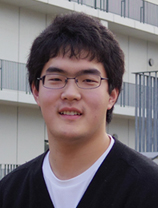 アメリカ合衆国の中間選挙で、ある立候補者がこんなことを言っていました。「立候補しないで結果に文句は言えない」。僕はテレビでこれを聞いて、自分が中学2年生の時に初めて総務委員長に立候補した時のことを思い出しました。僕は当時、教員と生徒の関わりようについて新しい仕組みを導入したいと考えていました。当時の総務委員会に投書して、間接的に実現してもらうやり方もありましたが、僕は翌年度の総務委員会に入って、自分の手で実現させる方法を選びました。それは当時の総務委員会が信用できなかったからではありません。もし仮に新しい仕組みが導入されなかったとしても、その結果に自分自身で納得したかったからです。投書をして一生徒としての意見を総務委員会に伝えるのも立派に生徒会活動に関わる行為です。しかし、やはり僕は自分の行動と結果を直結させたいという思いが強かったように思います。
アメリカ合衆国の中間選挙で、ある立候補者がこんなことを言っていました。「立候補しないで結果に文句は言えない」。僕はテレビでこれを聞いて、自分が中学2年生の時に初めて総務委員長に立候補した時のことを思い出しました。僕は当時、教員と生徒の関わりようについて新しい仕組みを導入したいと考えていました。当時の総務委員会に投書して、間接的に実現してもらうやり方もありましたが、僕は翌年度の総務委員会に入って、自分の手で実現させる方法を選びました。それは当時の総務委員会が信用できなかったからではありません。もし仮に新しい仕組みが導入されなかったとしても、その結果に自分自身で納得したかったからです。投書をして一生徒としての意見を総務委員会に伝えるのも立派に生徒会活動に関わる行為です。しかし、やはり僕は自分の行動と結果を直結させたいという思いが強かったように思います。 2016年度中央委員会議長、高校総務委員長の岡本明俢です。今年もあとわずかとなってしまいましたが、この場を借りて挨拶をさせて頂きます。
2016年度中央委員会議長、高校総務委員長の岡本明俢です。今年もあとわずかとなってしまいましたが、この場を借りて挨拶をさせて頂きます。
 「原点回帰」
「原点回帰」 2013年1月、総務委員が最初に集った準備会からずっと、目標として決めていることがあります。それは、「桐朋を盛り上げよう」ということです。今、桐朋は長い歴史の中でも、校舎建て替えという一つの区切りを迎えています。そのような転換期において生徒ができることとはなんだろうか、と考えた結果、桐朋を今よりもっといろんなことにチャレンジできる学校にしていこう!と考えました。
2013年1月、総務委員が最初に集った準備会からずっと、目標として決めていることがあります。それは、「桐朋を盛り上げよう」ということです。今、桐朋は長い歴史の中でも、校舎建て替えという一つの区切りを迎えています。そのような転換期において生徒ができることとはなんだろうか、と考えた結果、桐朋を今よりもっといろんなことにチャレンジできる学校にしていこう!と考えました。