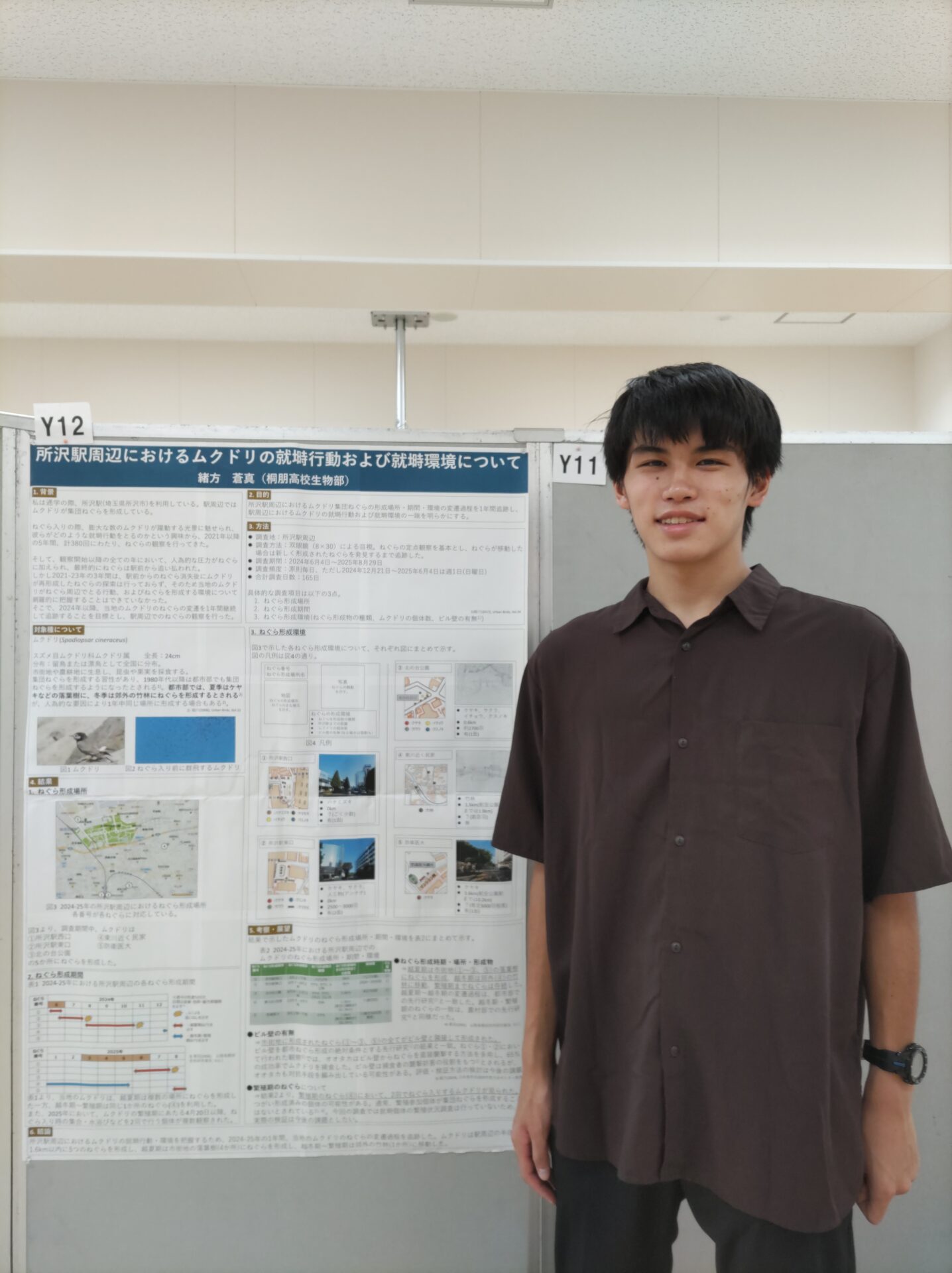高2緒方蒼真君が日本鳥学会2025年度大会でポスター発表を行いました。
TOHO Today高校
生物部の緒方蒼真君(高2)が9月12~15日に札幌の北海学園大学にて行われました日本鳥学会2025年度大会で「所沢駅周辺におけるムクドリの就塒行動および就塒環境について」というタイトルで高校生ポスター発表を行いました。緒方君から学会参加の振り返りと感想をもらいました。
高校2年の緒方です。僕は今回、日本鳥学会の高校生以下ポスター発表の部に「所沢駅周辺におけるムクドリの就塒行動および就塒環境について」というタイトルで参加してきました。
僕は昨年東京で開催された鳥学会にも同じくポスター発表で参加しており、今回の発表は、前回と同じテーマを、視点を変えて考察したものとなります。
研究テーマは、僕が日々利用している所沢駅に集団ねぐらを作るムクドリの生態について。駅前のロータリーに形成されたねぐらを毎日観察し、それを中1から今に至るまでの5年間にわたり続けてきました。昨年は、このうち中1〜中3までの3シーズンに得られたデータを、ムクドリ、オオタカ、コムクドリという、ねぐらに関わる3種の鳥類の視点から考察しました。
しかし話題が複数のものにまたがる以上、どうしてもトピックス的にまとめざるを得ず、全体として統一感に欠けていたのが昨年の発表の課題でした。
そこで今年の発表では、大きなテーマを所沢駅のムクドリねぐらの観察として昨年から引き継いだ一方、調査対象を「ムクドリがねぐらを駅前から移動した場合に、ねぐらを再形成する場所の傾向」の一本に絞り、そこから得られた結果・導かれた考察を、順を追ってできるだけ丁寧に展開していく方針で発表構想を練りました。
ポスター制作と口頭説明の準備は出発直前まで行い、札幌に着いた初日の夜はホテルで何度も直前練習を重ねました。発表時間をできるだけ短縮し、要点をなるべく的確に伝えることを目標に、当初の原形が半ば無くなるまで説明方法を改良しました。
それでもいざ発表となると、いくら参加2年目とはいえ緊張するもので、土曜日に2回行った発表ではなかなか思うように内容を伝えられた実感がなく、加えて周りの参加者のレベルの高さにショックを受けたこともあり、かなり落ち込みました。
それでも、土曜の発表が実践練習として効いたのか、翌日の日曜日になるとだいぶ要領を得て説明できるようになり、発表での聴衆とのコミュニケーションを楽しめる程度の余裕も生まれました。結果、土日の2日間を合わせて20人以上の方に発表を聞いていただき、多くの人から有意義な意見や指摘を頂くことができました。
中には著書を何度も繰り返し読んでいた憧れの研究者の方もおられましたし、また、僕と同じく自分の研究を発表しに来ていた高校生や中学生、小学生の姿もありました。
4日間の会期の間に、このように多くの鳥に関わる人たちと、会場の内外で、ときに議論を交え、ときに談笑し、語り合い、そして時間を見つけては鳥を観察したことを通じて交流できたのは、僕にとってかけがえのない経験になったと思います。そして、ここで生まれた人の縁は、いずれ必ず何かプラスのものを生み出す原動力になるだろうと期待しています。
前回同様、今回も多くの時間を自分の発表に割くことになったため、他の人の発表を聞きに行くことは満足にはできませんでした。それでも土曜日を中心に10件あまりの口頭発表と、高校生発表を主とするポスター発表を見て、その場で繰り広げられる議論を耳にすることができました。そこで多少なりとも新知見を得て、実際の現場における研究方法に触れて、なおかつそれらを楽しむことができたと思っています。
日曜の夜には自由集会があり、僕はオガサワラカワラヒワ(略称:オガヒワ)の保全集会に参加してきました。深刻な絶滅の危機に瀕するオガヒワ、その飼育繁殖に取り組む本土の動物園と、オガヒワの生息地である小笠原と、それぞれの現場で活動している関係者たちが顔を合わせて現状を報告しあい、今後の保全方針について議論するという趣旨の集会でした。正直なところ、僕は小笠原には一度も行ったことはありませんし、「保全」という取り組みについての何らの知見も持っていませんでした。ですが、わずかな期間に急激に個体数を減らしたこの鳥を守るため、事業計画を立てては即時実行し、それが確実に成果を生み出すまでフィードバックと改良を徹底する、事業関係者たちの活動姿勢からは、確実にこの鳥を絶滅の危機から抜け出させ、唯一無二の小笠原の自然環境を未来に引き継ぐのだという、「保全」に携わる人々の意志を感じることができました。
このように、今はまだ外部から眺めるしかなくとも、実際に第一線で活動する研究者の方たちの気概や活動姿勢を肌で感じ、今現在の最新の研究動向を知ることができたのは、今後の―いずれその中に加わりたいと考えている僕自身にとって、大きな意味のあることだったと思っています。
今後は、今回の学会で得たものを糧にして、常に僕自身の研究姿勢を省み、自分の知りたいことは何か、そのために行うべきことは何かを意識し続けながら、自分の研究に取り組み続けていきたいと考えています。
最後に、発表準備に関わってくださった生物科の宮下先生、茂木先生、僕の家族、今回の研究をご支援くださった桐朋学園同窓会の皆さま、そして日ごろから一緒に鳥を追いかけ、一緒に鳥について考え続けてくれている、生物部鳥類班の皆さんに、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。